1.シナプス分子抗体作成に至る道のり
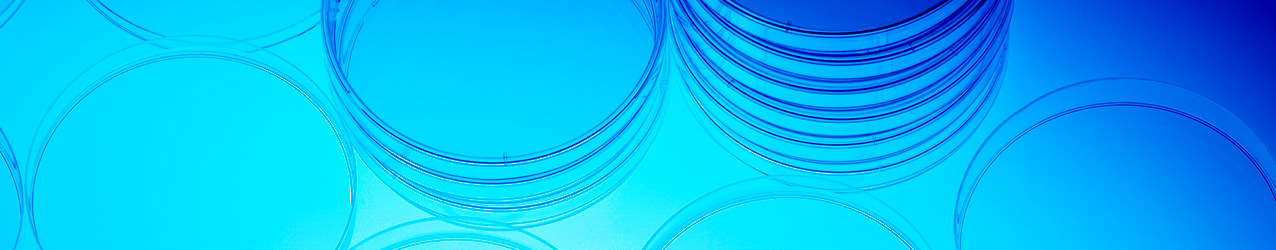
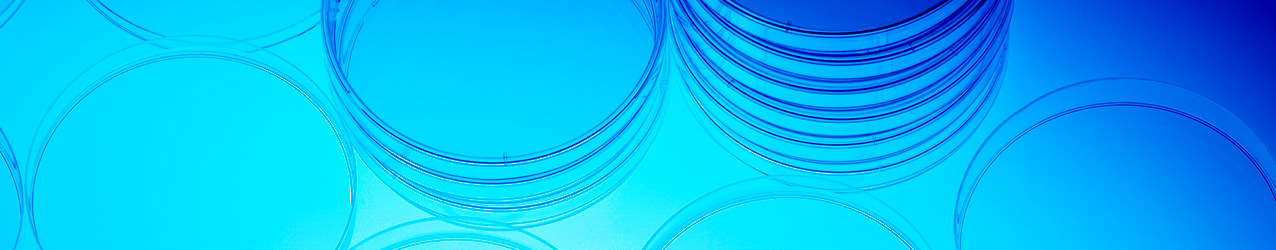
ニットーボーメディカルの研究用抗体「1.免疫組織化学用抗体(脳・神経系)」のリストにある抗体の殆どは、私がこれまで30数年間に作成し、学術論文等に発表してきたものである。実は、論文にしていないため未公開の物も含めると、リスト掲載数の倍くらいの抗体を作成してきた。このコラム紹介を始めるに当たって、神経解剖学の研究者の一人として、どのような経緯で抗体作成を行うようになったのか、時代背景とともに紹介したい。
私は、1984年に筑波大学大学院博士課程に入学し、内山安男助教授(その後、岩手医科大学、大阪大学、順天堂大学教授)をボスとする解剖学系ラボで4年間の大学院生活を送った。東北大学医学部後半の3年間も筑波大学のラボに泊まり込んで研究をしていたので、実質7年間筑波大学にいたことになる。学部時代と大学院の前半は、専ら膵臓などの分泌組織の細胞小器官の日内変動を、電子顕微鏡写真の定量学的形態計測法*1により解析していた。この時期は、ちょうど分子生物学が隆盛に向かって爆走し始める時期で、cDNAクローニングによる塩基配列とそれを用いた機能解析を示す論文がトップジャーナルに躍り出るようになっていった。当時の分子生物学は、日本はアメリカに次ぐ勢いがあり、特に神経情報伝達に関わる分野では、京都大学の沼正作先生、中西重忠先生、三品昌美先生らが綺羅星のように輝き、世界をリードしていた。その勢いは組織や細胞を扱ってきた解剖学、生理学、薬理学などの旧来からの学問体系にもパラダイムシフトを及ぼし、cDNAやプラスミドベクターを起点とする「遺伝子→分子→細胞」へのボトムアップ研究へ、生命科学の地殻変動を引き起こした。
そのような時代的潮流の中で、後半の大学院の研究テーマも大きく様変わりし、in situハイブリダイゼーション*2、光顕および電顕レベルでの免疫組織化学*3、タンパク質の単離精製と抗体作成など技術習得に邁進した。最終的に膵臓外分泌細胞の日内変動データとライソゾーム酵素の免疫組織化学データで博士(医学)の学位は修得できたものの、半減期が12年と長く放射活性の低い3H-dATPを用いたin situハイブリダイゼーションではシグナルが出たのか出なかったのかも分からぬまま未達となり、タンパク質の精製と抗体作成も結果を見る前に、大学院生活は時間切れ修了(終了)となった。しかし、未練となって積み残した大学院時代の2つの研究課題は、いくつかの幸運との出会いにより、その後の研究の柱になっていくことは実に不思議なものである。
大学院を修了し、1988年二人目のボスとなる金沢大学の近藤尚武教授(2年後に東北大学に異動)の下で解剖学教室の助手になった。そこで、発達期の小脳における神経特異的エノラーゼを組織化学研究する機会があり、プルキンエ細胞*4の樹状突起の見事な発育ぶりに感動し、現在に続くシナプス回路発達研究のきっかけとなった。1つ目の幸運は、近藤教授もin situハイブリダイゼーションの技術基盤確立を強く望み、そこに山形大学医学部を卒業したばかりのラガーマン後藤薫君(現在、山形大学教授)が大学院生として加わったことである。後藤君と二人で、当時は、ニックトランスレーション*5による35S-dATPを用いた放射性標識cDNAプローブによるin situハイブリダイゼーション実験に取り組んだ。半減期が87日となる35Sを用いることで、プローブ作成から乳剤オートラジオグラフィー法*6を用いた露光・現像による結果判定まで1~2ヶ月と短縮したものの、半年過ぎても一向に特異的シグナルは得られなかった。そんな中、組織中のRNA分解酵素が陰性結果の原因ではないかと考えた後藤君は、RNA分解酵素阻害剤をリストアップし、1つずつその効果を確認していった。その阻害剤の1つに2-メルカプトエタノール*7が含まれており、それをハイブリダイゼーション液に加えた実験において、CNPase*8の見事な発現シグナルが、オリゴデンドロサイトが分布する白質上に現れた。その他の阻害剤にはこのような効果は全く無いことから、その効果はRNA分解酵素阻害によるものではなく、2-メルカプトエタノールによる還元力による35S標識プローブ同士のS-S結合防止によるものであった。
これによりin situハイブリダイゼーションの基本技術が確立すると、クローニング、シークエンシング、プラスミド作成などの分子生物学の基本的研究技術の修得とそれによる自由自在なプローブ作成が、次の目標になった。そこで、助手二年目の1989年7月から8月の二ヶ月間を、新潟大学脳研究所の神経薬理学部門で訪問研修することになった。要するに、幼子二人と奥さんを金沢に残し、助手二年目の夏のボーナスを全部もらって新潟市内に4畳半を間借りし、布団と扇風機と少しの着替えだけをカローラに積んで押しかけたのである。今から振り返っても、それを許してくれた家族に、また惜しみなくアドバイスとサポートをいただいた神経薬理のスタッフ、技術職員、大学院生の皆さんに御礼を述べたい。2つ目の幸運は、この2ヶ月間の滞在がその後の研究方向性を決定づける連鎖反応を起こしたことである。
神経薬理で最もお世話になり親身に指導してくれたのが、当時助手であった崎村建司先生で、この出会いを通して生涯の研究仲間になった。その時、崎村先生から、間もなくPCR*9という遺伝子増幅法が世界中に広まり、プライマーという短いDNAを合成するだけで、欲しい遺伝子が誰でも手に入れることができるようになるという話を聞いた。これを聞いて、体に稲妻のような衝撃が走った。当時、組織化学に用いる一次抗体は主にそのタンパク質の単離精製を行った生化学者が作成し、その抗体を入手し研究に活用できるか否かは、生化学者との関係性にかかっていた。生化学者からしても、同じ研究目的で複数の研究者に同時供与できないという倫理的縛りもあるため、そうなるのである。そのため、一度抗体供与を受けたら重箱の隅を突付くまでその分子の発現局在解析をし続けるというのが当時の組織化学研究の仁義であった。しかし、PCRがあれば抗原となるアミノ酸配列をコードするcDNAを自ら増幅でき、それを家兎などの動物に免疫し、その抗血清から免疫グロブリンを抗原アフィニティ精製*10すれば、自由に抗体が作れるようになるのである。この夏を経て、分子解剖学的研究の方法論が実体化した。それは、クローニングやPCR法により解析プローブを作成して転写物の発現情報をin situハイブリダイゼーションにより明らかするとともに、その翻訳物の分子局在を抗体作成と免疫組織化学を駆使して明らかにするという研究戦略である。
新潟大学から金沢大学に戻って間もなく、神経薬理の担当教授として京都大学から三品先生が赴任してきた。それまで沼研の助教授としてニコチン性アセチルコリン受容体の分子生物学で名を轟かせていた三品先生は、脳研究所に着任するなりグルタミン酸受容体のクローニングを目標に定めた。三品研の崎村先生や大学院生が次々とクローニングしたcDNAに「イロハの◯番」という暗号が付され、その暗号遺伝子のin situハイブリダイゼーション解析を担当することとなり、グルタミン酸シナプス伝達研究に足を踏み入れることになった。さらに、三品研では、グルタミン酸受容体の遺伝子ノックアウトマウス*11作成にも一早く乗り出し、その解剖学的な表現型解析においても協力することになった。ここに至って、研究戦略のもう一つの柱となるグルタミン酸情報伝達系の形態生物学的研究も立ち上がることになった。この形態生物学というのは、私が作った造語である。そのキッカケは、ノーベル賞学者の利根川進先生との会話であった。共同研究が縁となって金沢大学に利根川先生をお招きした際に、利根川先生は「分子生物学のツールを使う研究者は数多いが、バイオロジーをやる分子生物学者は少ない」と述べた。それまでどこか分子生物学に引け目を感じる所もあったのだが、利根川先生のこの言葉そして昼夜を問わず研究に爆進する新潟大学脳研究所の分子生物学研究者の姿を見てきたことで、「そうだ、自分は形態学でバイオロジーをやればいいんだ!」と、心の底から吹っ切れた。
1992年、北海道大学医学部解剖学第1講座(井上芳郎教授は三人目のボス)の助教授として赴任すると同時に、グルタミン酸情報伝達系の分子解剖学と形態生物学の研究をスタートした。当初の予想では、分子解剖学研究は地味だが着実に積重ねることができる研究で、一方形態生物学研究は形態学的表現型が出るか出ないかのギャンブル的研究になるだろうと予想した。ところが、結果は逆で、グルタミン酸情報伝達の形態生物学研究こそ興味深い形態学的表現型が次々を見つかり、順調に論文化できた。一方、グルタミン酸情報伝達の分子解剖学をスタートしてから、最初の7年間は鳴かず飛ばずの状況に陥ってしまった。次回は、グルタミン酸情報伝達系のシナプス分子検出における重大な問題点ついてお話しする。
用語解説
